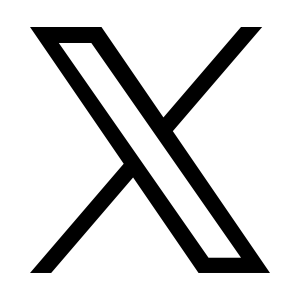LEADERS BLOG
最近の新幹線ではビジネス車両が導入されて、その車両はパソコン利用、Web会議など会話OK・携帯OKとなっていますね。
移動中にWeb会議もパソコン作業も気兼ねなくできるので有難いですね。
鉄道会社も時代のニーズに合わせてきているのだなと思います。
そうは言うものの、キーボートの音とか話す際には気を遣いますねと、本社で清水取締役と会った時にもそんな話をしていました。
そんな話をしたばかりの帰りの電車での出来事。
金沢から名古屋までの電車特急「しらさぎ」には残念ながらビジネス車両がありません。
その日の「しらさぎ」では、私の席の後ろの席でパソコン広げて仕事している30代くらいのサラリーマンがいました。
出発時から何やら仕事でトラブルでもあったのか、出発前まで電話で相手と話をしており、電話が終わると独り言で文句をボソボソと言いながら、パソコンのキーボートを爆音・超高速で叩き出しました。それがまたキーボードが破壊されるのではないかぐらいの強さなので、「ベートーベンか!」と突っ込みを入れたくなりました。
また音もミュートにしてないので、誤操作のたびにピロンピロン音も合わさって、「下手くそか!」とさらに突っ込みを入れたくなりましたが、まぁ彼もよほどトラブルが大変で追い込まれているのだろう、乗っている途中で騒音も終わるだろうと優しい気持ちでおりました。
ところが、何駅通過してもまったく終わる気配がなく、しまいにはキーボードを叩くたびに、まるで地震のように私の座席が揺れるほどエスカレートしてきたので、さすがに注意して(優しい目で)静かになりました。
ヒロユキ風に言わせていただくと、
そもそも彼は「周りに気を配れない・迷惑かけている意識もない」という時点で、日頃の仕事がうまくいっているとはとても思えない、だから電車でもあくせくと仕事しなくてはならない状況になっているのではないかと想像ができてしまいますね。
普段物静かで大人しい私としても無意識に周りに迷惑をかけていないかあらためて気をつけようと思った次第です。
「自由が嫌い!」という人は僕の周りにはあまりいないのですが、皆さんはどうですか?
僕もできれば自由に生きることができた方がいいなーと考えていますし、大切にしたい価値観の一つです。さて、ここで改めて「自由」とは何か?どんな状況が「自由」だと言えるのか?そんなことを考えてみました。
『自分の好きなことだけを好きな時に好きな人と(または一人で)好きなだけやれる状態』が「自由」だとしましょう。確かに「自由」な感じがします。
さて、いささか唐突ですが、僕の息子(3歳)は、おそらくこの「自由」が何かに妨害された!と感じた瞬間、泣いたりわめいたり踊り出したりしてかなり周りをげんなりさせます。彼の心中を僕なりに察しての勝手な解釈ですが(笑)
でも、いい大人はそんな振る舞いをするわけにもいきませんよね。
しかしながら、泣いたりわめいたりはしないまでも、同じようなことをしていないだろうか?!とハッとすることがあります。
例えば、
・機嫌が悪くなる
・不満な気持ちを態度に表す
・無視する
・あきらめる
などなど。
これは周りの人を困らせるような振る舞いではなかろうか?
泣いたりわめいたりする以上に質の悪い態度ではないか?
と、これは大いに猛省すべきだなぁ・・・とモヤモヤしていた時に、次のような言葉に出会うことができました。新聞のコラム欄に掲載されていたものですが、とても素敵で勇気づけられるメッセージだと思ったので、ここに内容を一部抜粋してご紹介します。
皆さんのこれからの人生を、楽しく充実した自由を実感できる時間にするための気づきになれば幸いです。
自由とは何か?
自分のことだけを考えて楽をする。それは「わがまま」。
つらいこと、いやなことはしない。それは「逃避」。
そうした生き方を続けていると自分の可能性はどんどん狭まり、逆に不自由になる。
困難の壁にぶつかっても希望を捨てない。自分らしく一歩でも一ミリでも挑戦を続け可能性を開いていく。その生き方にこそ真の「自由」と「満足」がある。
皆さんの誰しもが、毎日の仕事の中で様々な判断(judgment)をします。
この「判断」はどの様にして行うのでしょうか。
感覚?経験?なんとなく?・・・
その場その場における正しい判断は、決して適当な場当たり的なものでは出来ない筈です。
では、その「判断の基準になるもの」は何でしょう。
以前(そうとう昔)に読んだ本の中に「人生に必要な知恵は、すべて幼稚園の砂場で学んだ」と言う物がありました。
・何でもみんなで分け合うこと
・ズルをしないこと
・人をぶたないこと
・使ったものは必ず元のところに戻すこと
・誰かを傷つけたら、ごめんなさいと言うこと
など・・
つまらない、当たり前の事のように見えるかもしれませんが、どう生きるか、
どのように振舞うべきか、何を大切に日々を送るか・・・
仕事も人生も価値判断の基準も、すべては純粋な気持ちと目でしっかりと見れば、
自ずと正しい答えが目の前に現れるのではないでしょうか。
皆さん一人一人が、急がず慌てず、この「判断の原点」を心がければ、
もっともっと素晴らしい思いやりのある職場に成長できると感じます。

ある歌舞伎役者の方の話です。
その日も舞台が終わり
関係者8人で食事にいって、
楽しく過ごしていたらしいのですが、
違和感を感じたそうです。
せっかく8人で来たのに8人で会話を楽しむというよりは、
前後左右でバラバラに違う話題を話してる。
これはなんか違うのではないか?
照明が明るすぎるからではないか?
そう思った歌舞伎役者の方は、
照明が明るすぎるから消してみようと提案!
机の真ん中にろうそくの灯りだけにしたそうです。
そうすると不思議なことに
8人の距離が縮まり、一つの話題で
食事を楽しむことができたそうです。
これは何を意味するのか?
皆さんは何を感じますか?
実際に全体的に暗い中で局部的に照明される「あかりだまり」がある場合、
互いが近づいて会話しやすいなどといわれているそうです。
人と人とのコミュニケーションにおいて、周りや人の見え方を左右する
空間の照明には大きな影響があるようです。
私たちは「つながりが実感できる新たな別れのカタチをつくる」
をミッションにしていますが、
葬儀のさまざまな場面でどんな灯りがふさわしいのか、
灯りにも着目してみたいと思います。
コロナ禍でなかなかアクティブに動くことができないですが、新規感染者も減ってきて(今のところですが)、秋も深まり涼しくなってきたので訛っている身体をいかに健康に保っていけるか改めて考えてしまいます。
皆さんも身体は健康ですか?
最近知ったのですが、「体脂肪」と「内臓脂肪」は減らす方法が違ったこと。
運動すれば両方減るのかなと思っていたのですが。
体脂肪は運動(有酸素運動と筋トレ)で、内臓脂肪は食事(糖質・脂肪・塩分控える)で落とす。
これが、運動は比較的苦にならないのですが、運動した後に余計に食べたくなりますよね。
食べてしまうと体脂肪は落とせても内臓脂肪は落ちない・・。
毎日が意思と脂肪の戦い。
ただ健康でないと仕事も遊びもできなくなります。
健康第一ですね。
ちなみに顔ってどうすれば痩せるのでしょうか?
誰か教えてください。
- 2025.6
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6