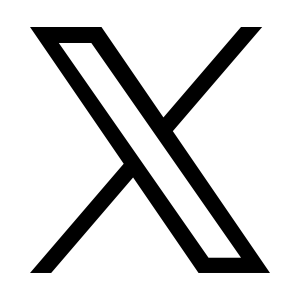LEADERS BLOG
哲学。
と書きはじめると、また訳のわからない事を言い始めるんだろうな、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな事ないのでサラッと読んでみてください。
哲学、って一言でコレ!と説明や理解することって難しいですよね?
一般的には、『どう生きるか?』『どうあるべきか?』『何でできているのか?』と真理を追求する学問と言われています。
『どう生きるか』って考えているようで考えてなかったり、はたまた考えすぎたり。とてもシンプルで当たり前に日々考えていそうだけど改めて自問すると深いテーマだと思いませんか?
さて、先日、三和物産のあるMTG(約10名が参加してもリモート会議)で『何のために仕事をしているのか?』という話題になりました。その時、おそらく参加者はいろんな想いが頭や胸に湧き出したのではないかと思います。なぜなら、今の今まで営業戦略や戦術を侃侃諤諤していた時の表情とは全く異なっていたから。営業戦略に関しては原理原則や市場や顧客など総合的に勘案して仮説を導き出せるのですが、『何のために仕事を?』という問いには原理原則ではなくあくまで自問自答だからなのでは、と私なりに解釈しています。
えー、何を言いたかったかというと、リモートMTGで哲学を論ずる僕たち三和物産ってマジメでしょ?!ということをお伝えしたかった、という内容でした(笑)
早いもので色々あった2020年も師走です。
日々流されるのではなく、どう生きるか?どうすればお客様のお役にたてるか?を考えて過ごしていきます。全集中で!
会ったことは無いけど僕がとても敬愛する人の一人に、出口治明さんという方がいらっしゃいます。ご存知の方も多いかと思いますが、かなりの読書家です。またご自身も様々な書籍を執筆されていて文化・歴史・宗教など様々なテーマでかなり骨太な内容のものが多く僕は大好きです。
さて、出口さんをはじめ私が尊敬する人が推薦する書籍は「読んでみようかな」と素直に思えるのですが、あまり興味がない人から『この本面白いから読んでみろよ』といわれると、あまり読む気はしません(というか絶対読みません)。だから僕もあまり「この本面白いから読んでみたら」と人に言うことはしないようにしています。
と、前置きしつつ、今回は1冊の本を読んで感じたことをお伝えしようと思います。別に推薦しているわけではありません。私の「感想文」程度に読んでみて下さい!
「ローマ人の物語」(塩野七生)という本があります。古代ローマ時代のことを教えてくれる内容なのですが、歴史というよりも当時生きてきた人が何を考えていたか?何をしたかったのか?そのパーソナルな部分を著者の主観で魅力的に描いている点がとても面白いんです。あと当時の風俗・風習などもわかってかなりの衝撃を受けました。
今から2,000年以上も前の時代に相続税、裁判、弁護士、上告、離婚、選挙、銭湯、劇場、ワイン(葡萄酒)、高速道路、利息、人間関係が原因での自殺、と言った概念やモノがローマ帝国には存在していたんです!なんかびっくりしませんか?紀元前の時代ですよ。
現在と比べるとテクノロジーや科学のレベルは全く異なりますが、人間の生活のベースになる基本的な部分はあまり変化はないんですよね。
・・え?そんなにびっくりしませんか?そうっすか。
まあ、何が言いたかったかというと、歴史や先人の方々の記録から謙虚に学ぶべきことはたくさんあるなぁ~、ということです。未来を見据えいろいろ考える事は当然のこととして、過去(歴史)を学びそこから気付きを得ることも、同様に、いやそれ以上に大切なことなのではないか、と最近特に感じています。
【追伸】
最近「鬼滅の刃」にはまってます。まだ最終話まで読んでないのでネタバレ的な内容を僕に伝えようとすることはやめてください。お願いします。
今回のブログは、かなり個人的な出来事とそこから感じたことです。
「落ち」も「教訓(?)」もありません。
(と、防御線をはらせてもらった上で)よかったら読んで下さい。
ちょっと前、スマホを買い替えました。
前回購入したのは、ちょうど三和物産に入社したくらいのタイミングだったので、約6年前。かなり久しぶりの機種変です。
いや、かなり衝撃を受けました。同じスマホなので基本的にはできることは同じなのですが、快適さ(使いやすさ・速さ・見やすさ)がケタ違い。すごいですね、ホントに。
で、早速「スマホ決済(QRとかバーコードとか)」をやってみよう!と、いろいろ調べ、アプリを入手し、チャージして準備完了。よし!使ってみようと実際に買い物をしてみました!
「うーん、まあ便利といえば便利なんだろうけどなんかめんどくさいなー」というのが本音。何がめんどくさいかというと、大丈夫かな?ちゃんと間違いなく決済されてんのかな?と毎回この不安と戦うことが「めんどくさい」。つまりこのシステムに対する信頼が僕には無いということが問題というか原因だと考えています。まあ、そんなめんどくさいこと考えずに「ピピッ」と使えばいいんですけどね(笑)
あらためて、人って理性(合理的かどうか)だけではなく感情(なんかいやだな)で動く生き物なんだなー、と実感しました。
はい、今回は以上です。
次回、気が向いたら「スマホ決済」を僕が活用できるようになったかどうかご報告します!
「翔ける。」
これは今僕たちが掲げているスローガンです。
「翔ける。」には、翔ける(飛翔)・架ける(つなぐ)・掛ける(かけ合わせる)という異なる3つの想いが含まれているんです。
(※詳細はコチラ!→http://www.sanwa-bussan.co.jp/concept/ )
さて、近頃「掛ける。」が活性化し様々な化学変化が起きているシーンを目にすることが増えてきました。
良い感じです!
例えば、
社内で使用しているシステムが使いにくいよね・・、という声を受けそれを解決する為のPJが立ち上がり定期的なMTGが実施されている、
とか、
生産部スタッフから営業部スタッフに対して、もっとこうした方がお客様のためになるのでは?一緒に考えませんか?という改善提案があり定期的にMTGを実施するようになった、
とか、
営業部内の部署をまたいだ勉強会が自発的に開催されるようになった、
とか。
他にたくさんの「掛ける。」が発生しています。僕はこの流れ、とっても好きだし、このように「掛ける。」を実践してくれている仲間に心からの敬意と感謝の想いでいっぱいです。
まだまだ小さい「掛ける。」かもしれませんが、「掛ける。」は一人ではできない点がキモ。複数人が集まってはじめて発生する事象なので、「掛ける。」が増え続ければ必ず大きな変化になると私は考えています。
これからも、社会✕お客様✕お取引先様✕新しい仲間✕まだ出会っていない人達✕三和物産の仲間、このような「掛ける。」を日々うみだし、社会も会社も自分も変化・成長させていきたいですね。
まあ、あまり難しいことは考えず、これからも「ちょっといいかな?」と気軽に仲間に声をかけていきましょう!
MTGや会議など会社のメンバーと話をする機会が、最近特に増えています。
今回は、そこで気付いたことをご紹介します。
「清水さん、なぜそのように考えたんですか?」とか「なんでそれをしようと思ったんですか?」と会話の中で聞いてくれる人がいます。つまり「なぜ?」という問いかけですね。
この「なぜ?」が出てくると、
『ああ、この人はとても真剣に考えながら僕と話をしてくれているんだな』と、
うれしくなったり、
『あれ?そもそもなんでそんなふうに考えたんだっけ?』と、
そもそもの本質を考え直すきっかけになったり、
とても豊かな会話になります。
でも「なぜ?」は、一方的だったり強引に納得させようとする会話の中からは生まれてこないことが最近になってわかってきました。そりゃそうですよね。「なぜ?」は興味や探求心の表れなので、どうでもよい話やキャッチボールができない会話からは出てくるわけがありません。
「なぜ?」が生れる豊かな会話ができているか?
をより意識しながら、これからも様々な人と関わっていきたいと思っています。
【補足】
僕はできるだけ「なぜ?」を会話の中で相手に投げかけるようにしているのですが、時に「なぜ(そんなことしたの?)」と叱責や否定のニュアンスが含まれてないかな・・・?と、ブログを書きながら考えてしまいました。
『これは興味や関心が伴った豊かな会話を生み出す「なぜ?」になっているか?』
ということを意識して使わないといけないな!と、
新たな気付きを得たところで、今回のブログはここまでと致します。
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6